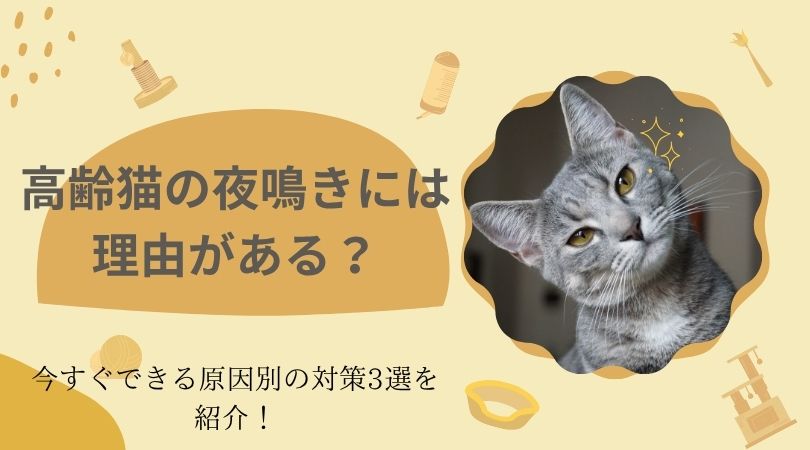高齢猫が夜中に突然鳴き出すと、「何か異常があるのでは?」と不安になる飼い主も多いのではないでしょうか。
実は、夜鳴きには年齢特有の理由があることが多く、放置しておくと猫にも飼い主にも大きなストレスになります。
猫と暮らしてきて20年のまことです。特にシニア猫のお世話は得意なので、このブログではその経験をいかし、情報発信していきます。

この記事では、高齢猫の夜鳴きの主な理由をわかりやすく解説し、原因ごとに今すぐ実践できる対策を3つ紹介します。
夜鳴きに悩む方は、ぜひ参考にしてみてください。
高齢猫が夜鳴きするのはなぜ?

高齢猫が夜鳴きをする背景には、加齢による心身の変化が大きく関わっています。
若い頃にはなかった症状が現れることで、不安や混乱を感じて鳴くようになることもあります。
ここでは、よく見られる主な理由を3つに分けて解説します。
認知症の影響による夜鳴き
高齢猫に多く見られるのが、猫版の認知症ともいえる「高齢性認知機能不全症候群」です。
昼夜の感覚が逆転したり、場所がわからなくなったりすることで、夜間に鳴き続けることがあります。
見当識障害や記憶力の低下が進むと、夜の静けさに不安を感じて鳴くこともあります。
不安や孤独感による夜鳴き
高齢になると感覚も鈍くなり、暗闇や静けさが強い不安を引き起こすことがあります。
特に飼い主が就寝中で周囲に誰もいないと感じると、安心を求めて鳴いてしまうケースがよく見られます。
また、視力や聴力の低下によって周囲の状況がわかりにくくなり、孤独感が強まる傾向もあります。
病気や体調不良が原因のケース
関節痛や内臓疾患、甲状腺の異常など、身体の不調が夜間に強く表れることもあります。
痛みや不快感があると、それを伝える手段として鳴くようになります。
特に、腎臓病や高血圧、甲状腺機能亢進症などは高齢猫に多く、夜間の症状として現れることも少なくありません。
原因別に見る夜鳴き対策3選

高齢猫の夜鳴きを改善するには、原因に応じた正しい対策を取ることが重要です。
ここでは、よくある3つの原因に対応した具体的な対処法を紹介します。
認知症対策:生活リズムと環境の見直し
認知症による夜鳴きには、昼間にしっかり活動させて夜に眠りやすくする工夫が有効です。
昼間は日光に当たらせ、軽い遊びを取り入れて体と頭を使わせましょう。
また、夜間は部屋を暗くしすぎず、安心できる明かりを残すのも効果的です。
環境を整えることで混乱を減らし、夜鳴きが緩和されるケースがあります。
孤独感対策:接し方と安心感の与え方
夜間の孤独感による夜鳴きには、就寝前のスキンシップや声かけが効果的です。
飼い主の匂いがついたタオルや毛布を寝床に置いたり、近くに寝かせることで安心感を与えることができます。
また、寝室にペット用ベッドを設置するなど、距離感を縮めることも有効です。
体調不良への対応:動物病院の受診タイミング
体調不良が疑われる場合は、早めに動物病院での診察を受けましょう。
特に夜鳴きが突然始まった、鳴き方が変わった、他にも異常が見られるといった場合は注意が必要です。
高齢猫は病気が進行しやすいため、早期発見・早期治療が何よりも大切です。
夜鳴きを放置するとどうなる?

夜鳴きは「歳だから仕方ない」と思われがちですが、放置してしまうと猫自身の健康や飼い主の生活に悪影響を及ぼすことがあります。
ここでは、夜鳴きを放っておくことで生じる3つのリスクをご紹介します。
ストレスによる体調悪化の可能性
夜鳴きを繰り返す猫は、何らかの不安や不快感を感じている場合が多く、放置することでストレスが蓄積します。
慢性的なストレスは、免疫力の低下や食欲不振などを引き起こし、体調をさらに悪化させる恐れがあります。
飼い主の睡眠不足による影響
猫の夜鳴きが続くと、飼い主の睡眠の質が下がり、日常生活に支障をきたすことがあります。
睡眠不足が続くと、イライラや疲労感が蓄積し、猫との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
互いの生活の質を守るためにも、対策は必要です。
ご近所トラブルにつながるリスク
集合住宅に住んでいる場合、夜間の鳴き声が隣人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
飼い主が気づかないうちにクレームにつながることもあり、トラブルの原因となるケースも少なくありません。早めの対応が重要です。
高齢猫の夜鳴きを減らすための生活習慣

高齢猫の夜鳴きを根本的に減らすには、日常生活の見直しが効果的です。
日々のちょっとした工夫が、猫の安心感と快適さにつながります。ここでは、取り入れやすい生活習慣を3つ紹介します。
規則正しい生活リズムを作る
高齢猫でも、毎日決まった時間にご飯や遊び、トイレの時間を設けることで、安心感が生まれます。
特に日中の活動量を増やすことで、夜にしっかり眠れるようになります。
照明の調節で昼夜の区別をはっきりさせるのもおすすめです。
食事やトイレ環境の見直し
空腹やトイレの不快感も夜鳴きの原因になります。
寝る前に少量のフードを与えたり、トイレを清潔に保つなどの配慮が重要です。
また、高齢猫に合わせたフードや低い位置に設置されたトイレなど、身体に負担をかけない工夫も取り入れましょう。
安心できる寝床の工夫
静かで暖かく、身体にフィットするような寝床を用意することで、夜間の不安を軽減できます。
飼い主の匂いがついた毛布やクッションを使うのも効果的です。
また、寝床の近くに薄明かりをつけておくと、視力の衰えた猫も安心しやすくなります。
高齢猫の夜鳴きには、認知症や不安、病気などさまざまな理由があります。
鳴くのには必ず意味があり、それを正しく理解して対処することが、猫と飼い主の快適な生活につながります。
獣医に相談すべきタイミングとは?

夜鳴きが体調不良によるものであるかを見極めるには、いくつかのサインに注目することが大切です。
以下のような変化が見られた場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
- 夜鳴きが突然始まった、または鳴き方が変わった
- 食欲不振、体重減少、粗相など他の異常が見られる
- 高齢猫で定期健診を受けていない
また、夜鳴きが続いているが原因がわからない場合や、鳴き声が急に減った場合も注意が必要です。
病気の初期サインを見逃さないためにも、「少し気になる」段階で相談することが、猫の健康を守る第一歩になります。
まとめ
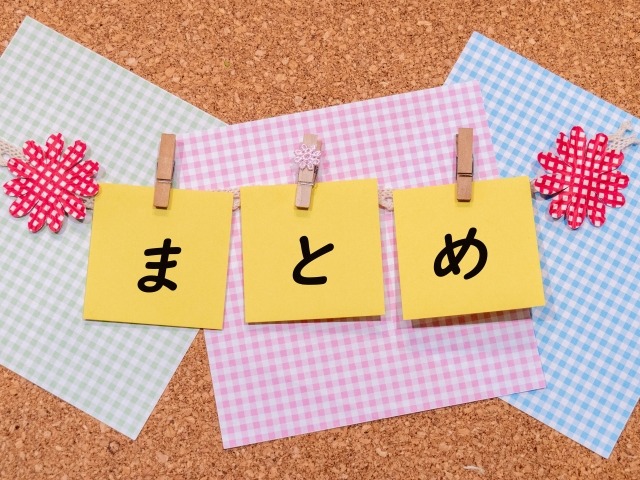
高齢猫の夜鳴きには、認知症や不安、病気などさまざまな理由があります。
鳴くのには必ず意味があり、それを正しく理解して対処することが、猫と飼い主の快適な生活につながります。
この記事で紹介したように、生活リズムや環境を見直すだけでも改善が期待できます。
夜鳴きに悩んでいる方は、ぜひ今日から一つでも行動を起こしてみてください。
あなたの優しさと工夫が、愛猫の夜の不安を和らげる大きな一歩になるはずです。